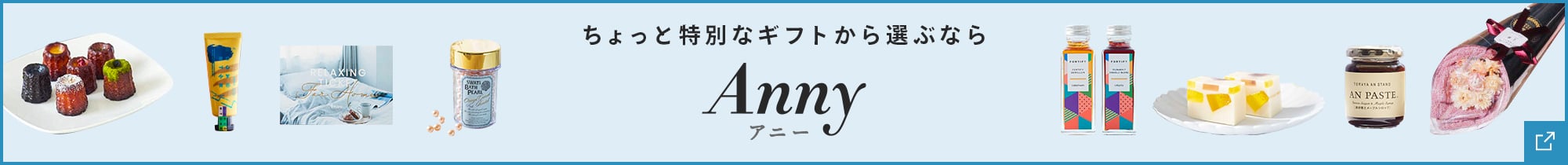- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
伝・甘露寺親長古筆切
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
商品説明 「甘露寺親長卿」の極め札がある古筆切。明応9年(1500)8月17日の和歌であるという。甘露寺親長かんろじちかなが一四二四 - 一五〇〇室町時代後期の公卿。応永三十一年(一四二四)生まれる。父は頭左大弁房長。康正二年(一四五六)から明応二年(一四九三)にかけて長く陸奥出羽按察使(都護)の職にあり、その名で各記録にみえる。同時代の三条西実隆は甥、中御門宣胤は娘婿といったように、当時の実務家的廷臣の中心的存在。永享のころ叙爵されて以来宮中に祗候し、嘉吉三年(一四四三)九月南朝遺臣と称する輩が宮中に乱入した際、太刀を抜いて防戦したのは有名。翌文安元年(一四四四)右少弁に任ぜられて以来、弁官時代に朝儀の勉強に励んだようである。享徳元年(一四五二)参議、翌二年権中納言、また長く賀茂伝奏を勤めた。応仁の乱で邸が焼かれ、文明二年(一四七〇)避難先の勧修寺・石山寺・鞍馬寺もつぎつぎに罹災し、特に鞍馬においては家蔵の文書記録類をすべて焼失した。同年九月帰京、再び朝廷に出仕し、みずからも諸役を勤めるほか、朝儀の故実に精通しているところから若い廷臣の指導をした。寛正六年(一四六五)権中納言を辞して以来、位は文明元年正二位に昇ったが、官の方はたびたびの推挙を「高官無益也」(『親長卿記』文明三年四月二十六日条)といって断わっていた。明応元年嫡子元長はじめ周囲のすすめでやっと権大納言昇進を受けたが、翌二年にはすべての官職を辞し、八月二十七日に出家、法名は蓮空。同九年八月七日没した。七十七歳。日記に『親長卿記』があるほか、諸記録類の写本があり、その内有名なのは『園太暦』で、同記の現在みられるのは大部分親長の写本によるものである。(『国史大辞典』)
残り 1 点 7000.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 05月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-